カテゴリー
- お便り (3)
- アート (11)
- カフェ (36)
- セレクション (7)
- ハンドアウト (6)
- ファッション (9)
- フォト・ギャラリー (3)
- 健康 (294)
- 出版 (56)
- 図書 (67)
- 国際 (14)
- 大学 (177)
- 季節 (168)
- 学会 (393)
- 将棋 (61)
- 帰国 (23)
- 意見 (113)
- 技術 (325)
- 旅 (651)
- 日常 (714)
- 渡欧 (43)
- 渡米 (318)
- 研究活動 (1057)
- 研究活動技術 (2)
- 研究論文- (35)
- 禁煙レストラン・カフェ (8)
- 英語 (41)
- 言語 (173)
- 言語学者 (7)
- 読書 (59)
- 講義 (471)
- 買い物 (24)
- 運動 (221)
- 雑感 (440)
- 音楽 (8)
- 音楽- (890)
- 食 (75)
Copyright 1997-2010 Hisao Tokizaki.
Page generation : 0.1718 seconds.


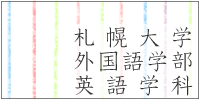

『ポピュラー音楽作曲のための旋律法』という本を買って読んでいます。最初のところで、メロディーは、五線譜のように左から右に一目で把握されるものではなく、時間を追って1音ずつが順番に聞こえるのであり、次にどういう音が来るかは、聞くまでわからないのだ、ということが書かれていました。ああ、これは、まさに僕が先週の講演で言語について話したのと同じこと。言葉も書いてしまえば、左右に一覧できるけれど、音声では次にどういう言葉が来て、どういう構造になるかは、時間順にしか、わからないのです。それをわかりやすくするために、人は・・というのが話のポイントでした。また、機会があれば書きたいと思います。